診療部門紹介

特定機能大学病院の循環器診療部門として狭心症、心筋梗塞、不整脈、心臓弁膜症、心筋症、心不全、肺高血圧症、先天性心臓病などあらゆる循環器疾患に対して高い専門性を生かした高度・最先端の治療を行っています。
地域医療に貢献すべく、24時間365日いつでも迅速に緊急疾患に対応し、心臓血管外科をはじめとした他診療部門と協力した集約的治療体制を整えています。
「かかりつけ医」との連携を充実させ、九州全域にわたる地域関連病院との総合診療を実現しています。
循環器病センター外来
施設概要
循環器病センター外来では、心臓の病気(胸痛、脈の乱れ、心電図異常など)、生活習慣病(血圧・血糖・コレステロールの異常など)、血管の病気(動脈硬化、動脈瘤、静脈瘤など)等が対象となり、年間約22,000人の受診があります。
また、同センターでは「人間ドック」の受付も行っています。
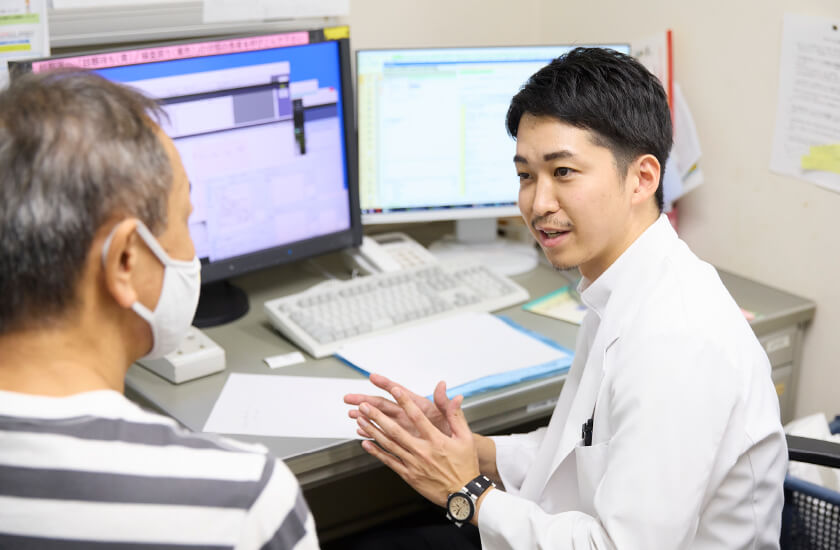
特徴
心臓・血管内科(毎日)、心臓・血管外科(火曜日と木曜日の午前)、小児科(金曜日の午後)、環境医学(月曜日の午後)が合同で集学的外来治療にあたっています。内科系外来では重症心不全、虚血性心疾患、不整脈、難治性高血圧、肺高血圧症、血管新生といった各種循環器疾患を対象とした外来を設けております。
事前にかかりつけ医より「紹介予約センター」もしくは「循環器病センター」へのご連絡を頂ければ、検査を含めた受診日時や適切な担当医の決定も行うことができ、スムーズな外来受診をご提供することが可能となります。
また、冠動脈CT(毎日午後)や心筋シンチ(月曜日と水曜日の午前)、運動負荷試験(毎日午前)、24時間ホルター心電図(毎日)、24時間血圧計(毎日)などの検査予約に関しても学外からの電話予約が可能となっておりますので、お気軽にご連絡ください。何かご不明な点やご質問ございましたら、お気軽にお電話などにてお尋ねください。
心臓・血管内科病棟

当科では年間1,300-1,500例と非常に多くの入院患者を受け入れており、その疾患も非常に多岐に渡り、大学病院としても全国でも指折りの施設です。当院は植込み型人工心臓の手術認定施設でもあり、心移植を前提とした重症心不全症例も多く、循環器疾患で経験できないものはないといっても過言ではありません。病棟ではチーム制を取り、各指導医や各専門グループと常にディスカッションしながら治療方針を決定しており、循環器診療ではこのようなチーム体制が非常に重要で有効と考えています。専攻医や研修医に対する教育にも積極的に取り組んでおり、循環器系検査や疾患のレクチャー、トレーニング及び支援医師(メンター)による面談を行い、日々成長を実感してもらえる体制を目指しています。そして病棟医の人数が多く、チーム制を採用していることで結婚・出産される女性医師も働きやすく、また多職種含めたレクリエーションも行うなどみんなが仲が良く明るく楽しい職場です。
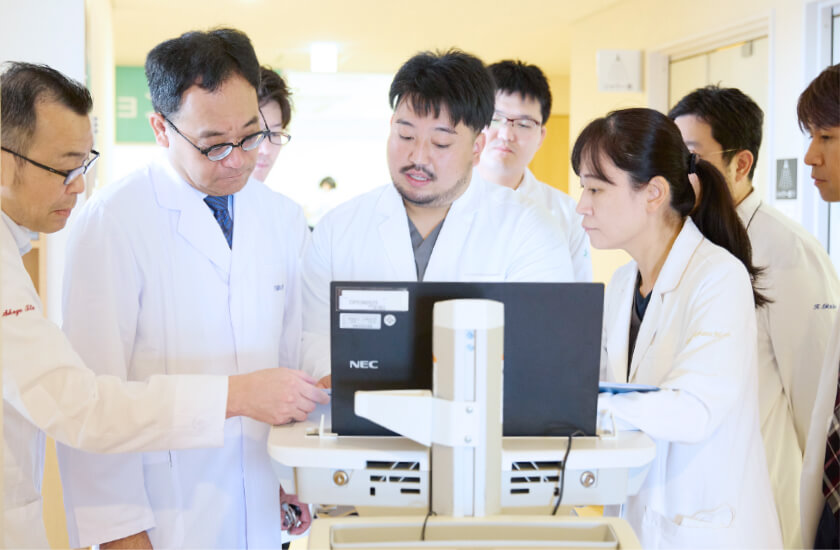
心臓リハビリ病棟
(西11階混合病棟)
施設概要
心臓リハビリ病棟では、心臓リハビリテーション、下肢末梢動脈疾患治療、ペースメーカ電池交換が必要な患者様を対象とした診療を行っています。リハビリ室では、当科病棟入院中の虚血性心疾患、重症弁膜症、下肢末梢動脈疾患を含む心血管疾患、心血管疾患術後、肺高血圧症の患者様を中心に積極的に運動療法の介入を行っています。
特徴

久留米大学の心臓リハビリテーション
古くは心筋梗塞患者に対する運動療法は左室リモデリングを助長すると考えられていた1956年当時、日本内科学会において久留米大学第三内科(現在の心臓・血管内科)の木村登初代教授が心筋梗塞後急性期を過ぎた患者に対する積極的運動療法と食事療法などを包括したリハビリテーションの重要性を述べられた事に始まります。1982年には二代目教授である戸嶋裕徳先生が当時としては画期的な心筋梗塞4週間リハビリテーションプログラムを作成されました。そして現在に至る長年の間、心臓・血管内科はより良い心臓リハビリテーションの探求と提供を行っています。
重症心血管病と術後の回復をサポートします
心臓弁置換術、冠動脈バイパス術などの心臓手術症例、大動脈瘤、大動脈解離に対する大血管手術症例、また高度救命救急センターで急性期治療を経た急性心筋梗塞リハビリテーションも行います。
心臓リハビリテーションは身体機能の回復だけでなく、QOL(生活の質)の向上や再発予防も目標としています。
病棟には広々とした心臓リハビリテーション機能訓練室を設けており、有酸素運動を行うための自転車エルゴメータなど充実した最新機器を備えています。
高度救命救急
センター・CCU

CCU(心血管集中治療室:Cardiovascular Care Unit)は久留米大学病院高度救命救急センター内において循環器救急疾患の初療と入院後集中治療を担当している部署として活動しています。救命センター開設時の1981年(昭和56年)6月に開設され、40年以上の歴史のある部署となります。スタッフは全員が心臓・血管内科に所属しており、CCU専属で循環器救急・集中治療に従事している日本でも数少ない施設となります。心臓血管系救急疾患はもちろん、敗血症・呼吸不全・腎不全などの併存疾患に対しても対応しており、体外式膜型人工肺(ECMO)や補助循環用ポンプカテーテル(Impella)を含めた補助循環の管理も一貫してCCUスタッフで行っています。CCUスタッフのみで対応できない全身合併症などに関しては心臓血管外科・救命救急センター他診療科を含めた大学病院内各診療科と連携して治療を行っています。もちろんあらゆる重症度の患者について相談頂ける体制をとっており、心臓・血管内科病棟や関連病院と連携して、病態に応じて適切な精査、加療を提供できるよう心がけています。
循環器病研究所
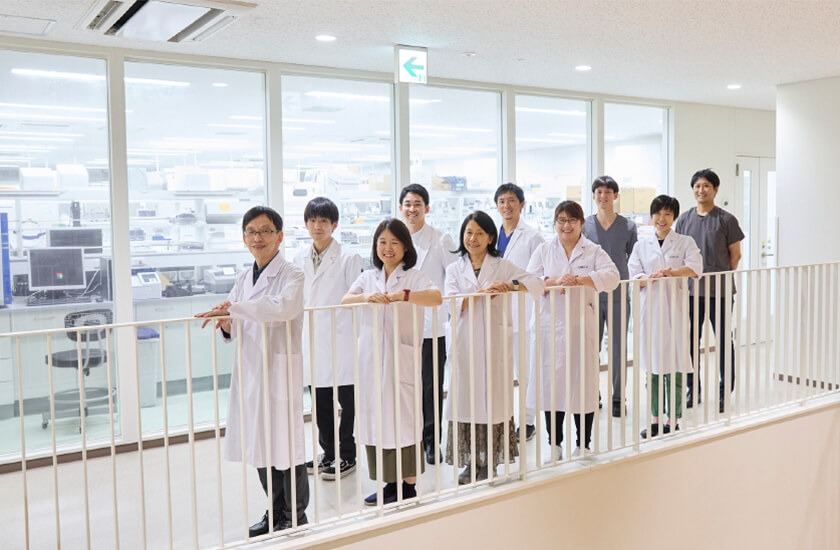
循環器病研究所(循研)は「今ないものを世の中に」を標榜しており、循環器病の解明に挑戦する若手のために、自らを高め仲間と協力して問題を解決していく場を提供しています。その挑戦から生み出される新たな研究成果、そして力をつけた若者を世に送り出すことが循研の使命です。
循研は我が国の循環器病克服を目的に1959年に久留米大学医学部の研究所として設置されました。その後、数回の改組を経て現在では大学直属の附置研究所となっています。
現在の循研では循環器系診療科(内科、外科、小児科)の若手医師が各診療科の問題意識を背景とする多様な研究に取り組んでいます。循研には分子・細胞・組織・個体レベルの分析を行うため種々の機器が設置されており、技術と知識を備えた専任スタッフが高度な研究を支援しています。